日本企業のDXの特殊性を考える
組織変革について、研究者や実務家によって様々な知見が蓄積されています。今回は、それらの知見をベースにしながら、組織変革としてのDX(デジタル・トランスフォーメーション)の特殊性について、考えてみたいと思います。
DXとは、デジタル技術を用いて変革をもたらすことであり、企業から見れば、組織変革の一つに位置づけられます。そのため、DXを成し遂げるためには、過去の組織変革の知見の適用を検討することが第一歩となります。具体的には、DXで何を成し遂げたいのかの「方向性」を示し、その方向性を従業員が腹落ちするように「コミュニケーション」を行い、その方向性をサポートする「仕組み(例:組織、教育、評価)」を導入する、というものです。DXでも、こうした「王道」を起点とすることは有用だと思われます。 とはいえ、DXという新しい現象であれば、既存の組織変革とは異なる特殊性があるかもしれません。そうした特殊性を理解せず、これまでと同じと高を括っていると、思わぬ落とし穴にはまる可能性もあります。そこで今回は、日本企業におけるDXの特殊性を、二点議論したいと思います。

特殊性その1:デジタル技術に関する「知識」と組織内の「パワー」の不一致
日本企業におけるDXの特殊性の一つ目は、変革のコアとなるデジタル技術に関する「知識」を持った人が、組織内で「パワー」を持ちづらいことです。DXは、新手法・新技術の導入を伴う組織変革です。しかし組織構成員の全員がデジタルのような新技術を深く理解しているわけではありません。新技術を理解できない従業員が、かつてのやり方にこだわる抵抗勢力になることもあります。そうした中で変革を推進するには、新たな技術を理解している人にパワーや資源を与えて、抵抗勢力を説得させたり、または排除させたりする必要があります。または、パワーを持った人にその技術の有用性を理解させて支援を得ることも有効です。いずれにしても、「知識」と「パワー」を一致させることが重要になります。
しかし、前述の通り、日本企業ではデジタル技術に関する「知識」と組織内の「パワー」が一致しないことが多々見られます。まず、若者の方がデジタルに慣れている傾向があるにも関わらず、年功序列ゆえに、彼らがパワーを持ってDXを推進することは自然発生的には起きづらいです。同様に、伝統的な日本企業におけるIT部門は、社内で大きなパワーを持っていないことが多いです。さらに、外部コンサルタントも知識はあっても社内においてパワーを持つわけではありません。デジタル技術に関する「知識」と組織内の「パワー」が一致しづらい状況にあるかもしれないことを理解したうえで、両者の一致を考えることが、日本企業のDXにおいて求められると言えます。

データを用いて問題発見から課題解決に至るまでの仮説構築、組織変革力を養成
特殊性その2:組織内の意思決定プロセスの変化
日本企業におけるDXの特殊性の二つ目は、組織内の意思決定の在り方が変わる可能性があることです。デジタル技術を通じて、様々なデータを入手・分析できるようになると、データに基づく議論がベースになります。データに基づく分析結果は、過去の事実から得られたものであり、個人の感情に左右されるものではありません。そのため、「自分の決定に間違いはない」とパワーで意思決定をしてきた個人に対して、本当にそれが正しいのかを議論する余地が生まれます。今までパワーで押し切られていた意思決定が、一歩前進することになり、健全な意思決定が促されるのです。いわば「データに事実を語らせる」ことで、パワーを持った主体による意思決定の歪みを抑えられるのです。特に忖度が多いと言われる日本企業にとって、こうした意思決定プロセスの変化は特筆すべきものであると言えます。
しかし、「データを元にどう組織内で意思決定をするか」の議論は、まだ不十分だと感じます。近年、データを元にした予測の議論(AI等)は活発ですが、その予測結果を元に、どのように意思決定をするかについても考えなければなりません。ただAIの予測に従うだけであれば、経営者は不要です。AIの結果は過去の傾向を踏まえた「確からしい」参考情報の一つに過ぎず、マネジメント層は時にはそれに反する意思決定をすべきこともあります。そのため、データや分析結果を元に、誰が、いつ、どのような議論をするのか、その議論を通じてどのように意思決定をするのかといった一連のプロセスを、改めて検討しなければなりません。さらには、意思決定の参考になるデータとは何かという議論も必要です。時に属人化しうる日本企業の意思決定プロセスをどう標準化するのかの議論は、DXによってより際立つ課題かと思います。

以上、DXの特殊性を議論してきましたが、組織変革の王道を理解しながらも、その時々の特殊性を踏まえてマネジメントするのは簡単ではありません。そこで、こうした議論を行うために、筆者の所属する東京大学では、「DXと企業経営」に関する寄付講座(ベイカレント・コンサルティング寄付講座)を設置しました。皆様も組織変革におけるDXの特殊性について改めて考えてみませんか?(第3回に続く)
本連載は、東京大学大学院の大木清弘准教授(2017年度から2024年度まで「経営戦略コース」のグループ指導講師を担当)に執筆いただき、生産性新聞に掲載された記事です。
生産性新聞2024年5月25日号:連載「組織変革の羅針盤」掲載分
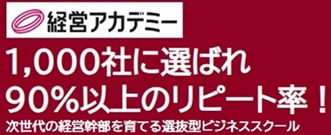
経営アカデミーは、企業派遣向けの選抜型ビジネススクールです。卓越した研鑽とネットワーキングプログラムを通じて・・・

経歴:
2007年東京大学経済学部卒業。08年同大学大学院経済学研究科修士課程修了。11年同大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。12年同大学より博士(経済学)。関西大学商学部助教、東京大学大学院経済学研究科講師を経て、20年より現職。専門は国際経営論、国際人的資源管理論。2009年国際ビジネス研究学会優秀論文賞、15年国際ビジネス研究学会学会賞。著書に『コア・テキスト国際経営』(新世社)など。












