本コラムの要点
・多くの企業はCSデータを収集していますが、企業によって活用度合いにバラつきがあります
・CSは企業業績にプラスの影響を与えますが、業績に影響する要因は他にも多数あります
・勘と経験に頼ったサービス品質の向上から、CSデータを活用した品質向上への転換を進める必要があります
・CSデータの収集、分析、普及、活用というCSデータマネジメントは、様々な要因によって実践方法が大きく異なるため、自社に適した方法を模索されることをお勧めします
・実践方法を模索する際は、CSデータマネジメントの好事例から学ぶことをお勧めします
企業における顧客満足度データの活用は進んでいるのか?
「日本の私設迎賓館として…世紀を超えて受け継がれてきた「おもてなし」を追求し、お客様にご満足いただけるよう努めてまいります。」(帝国ホテル ※1、 …は省略部分)
「際立つ技術と品質:樹脂加工および住宅分野で永年培った差別化技術と提供するハード(製品)、ソフト(サービス・ソリューション)の両面でお客様に満足いただける品質が強みです。」(積水化学工業 ※2)
企業の規模や業種に関わらず、顧客満足を重視することは経営において当然だと考えられています。また、我が国において、産官学の叡智によって開発された日本版顧客満足度指数(JCSI)調査の他、様々な顧客満足度(Customer Satisfaction:CS)調査が普及し、多くの企業がCS調査を利用しています。
しかし、サービス分野の専門家は、企業がCS調査の結果を上手く活用できない問題(CS調査やりっぱなし問題|松井サービスコンサルティング)や、CS調査を行う前に仮説を作成する重要性(効果的なCS調査(顧客満足度調査)とは:その手法やポイントを解説 | 生産性navi)を指摘しています。それでは、なぜ企業はCSデータを活用できないのでしょうか?どうすればCSデータを活用でき、サービスをより良くすることができるのでしょうか?
本コラムでは、これらの問いに答えていきます。はじめに、企業経営におけるCSの重要性に関する主要な議論を要約します。次に、CSを高める手段としてサービス品質向上に注目し、その課題としてサービス品質の「効果」視点と「コスト」視点について説明します。最後に、CSデータを活用したサービス品質向上プロセスであるCSデータマネジメントとCSデータマネジメントのお勧めの学び方について説明します。
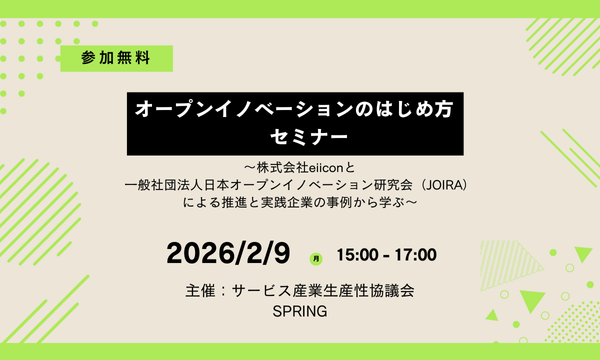
なぜ顧客満足が重要なのか?
CSは株価、利益、市場シェアという企業業績にプラスの影響を与える要因の一つです(Otto et al., 2020)。CSと企業業績の関係は複雑ですが、CSが企業業績、特に利益に影響するメカニズムについては「売上の向上」と「販売管理費の削減」という2つの主要な視点があります(重松, 2022)。
・売上の向上:高いCSが顧客の再購入意向を高め、売上向上を通じて企業の利益を押し上げる
・販売管理費の削減:高いCSを獲得し、いわば無料の宣伝効果のように肯定的な口コミが顧客により拡散され、企業の販売コストの低下を通じて利益を押し上げる
しかし、CSが企業業績に与える影響は、業種や満足度の測定方法など様々な要因によって変化することや、CSだけで企業業績が決まるわけではないことが明らかにされています(Otto et al., 2020)。満足度の測定方法に関しては、企業の実務でよく使用されているCSの平均値を高めることよりも、「大満足した顧客」を増やすことの方が企業業績とより強い関係を有すると報告されています(Otto et al., 2020)。この大満足した顧客とは、例えば5段階評価でCS調査を行った場合、最高評価の「5」をつけた顧客のことで、「top box」と呼ばれています。
CSが企業業績に貢献したり、大満足した熱狂的な顧客が企業にも貢献したりするため、CSは企業経営において無視できない要因です。しかしながら、CS向上のための戦略策定やその実行には多額の投資が必要な場合があり、科学的な観点を取り入れた冷静な検討が必要です。次項では、CS向上戦略としてサービス品質に注目し、サービス品質に関わる効果視点とコスト視点を説明します。

SPRING会員について(会員のメリット・入会方法)
当協議会はサービス産業のイノベーションと生産性向上を目指して国民運動を推進致しています。
サービス品質向上による顧客満足向上の問題:サービス品質の効果視点とコスト視点
サービス品質は、顧客が知覚するサービスの良し悪しのことで、CSに影響する主要な要因であることは多くの文献(例:Hogreve et al., 2017)で支持されています。サービス品質について顧客は、プロセスに対する期待と、成果に対する期待を抱いています(Lovelock & Wirtz, 2008)。飲食店で例えると、丁寧な接客を受けたい(プロセスへの期待)、素晴らしい料理を楽しみたい(成果への期待)というように、顧客はプロセスと成果のそれぞれに期待を抱いています 。さらに接客に関する研究では、顧客は、店内が混雑しているときは従業員の対応の速さを重視し、空いているときは接客の丁寧さを重視する傾向が報告されています(Lucia-Palacios et al., 2020)。したがって、ある飲食店がサービス品質を高めたいとき、状況や個人によって異なる顧客の期待を捉え、その期待の水準を満たす品質を実現しなければ高いCSの達成は難しいと考えられます。そして、サービス品質を向上させたければ、従業員を支援し、教育することが不可欠です。

経営的に重要なことは、従業員を支援し、教育する背後にはコストが発生している点です。例えば、従業員研修を行う場合、研修費用だけでなく、参加した従業員の人件費もコストとして発生します。サービス品質を高めることでCS向上を達成するという効果視点だけでなく、サービス品質向上のための投資により利益を圧迫するというコスト視点も検討する必要があります。
サービス品質を改善する問題は複雑だからこそ、CSデータを活用して顧客から評価される品質を特定したい企業は多いのではないでしょうか。なぜなら、サービス品質を向上させたにも関わらず、期待していたCS向上を達成できない場合、企業利益を低下させる可能性があるからです(Hogreve et al., 2017)。したがって、企業はサービス品質に投資する際、費用対効果を考慮して効率的にCS向上を達成できるような仮説を立てることが求められます。つまり、勘と経験に頼ったサービス品質向上から、CSデータを活用した品質向上への転換を進める必要があります。
次項では、CSデータを収集・分析し、社内で広め、活用するという一連のプロセスであるCSデータマネジメントについて説明します。

顧客満足データマネジメント<収集、分析、普及、活用>
マーケティングの主要な雑誌であるJournal of Marketingに掲載された論文によると、CSデータマネジメントは、「CSデータの収集」、「CSデータ分析と腹落ち」、「情報交換によるCSデータの普及」、「CSデータの活用」という4つの活動で構成されています(Morgan et al., 2005)。それぞれの活動で推奨されていることを表にまとめました。
まず、CSデータの収集段階では、データを収集するにあたって、全社的に標準化された方法があること、高頻度で収集することが推奨されています。次に、CSデータの分析や腹落ちの段階では、自社の現在と過去のCSを比較するだけでなく、CSの向上要因を明らかにするために多変量解析などの統計的手法を用いた分析が推奨されています。このとき、分析結果の解釈ができなければCSデータの活用は困難なため、実証分析の知識と自社サービスへの深い理解の両方が必要です。その次に、情報交換によるCSデータの普及段階では、少なくともCSデータを四半期に1回、社内に発信することが求められます。最後に、CSデータの活用では、CSデータ分析と腹落ちの段階で明らかにされたCSの向上要因に働きかける施策を策定し、実践する必要があります。
| 段階 | CSデータの収集 (Scanning) | CSデータの分析と腹落ち(Analysis) | 情報交換によるCSデータの普及(Dissemination) | CSデータの活用 (Utilization) |
| 推奨事項 | ・データを収集する標準化された仕組み ・データを頻繁に収集 | ・CSの向上要因を特定する統計的分析 | ・CSデータを少なくとも四半期に1回共有 | ・CSデータがサービスの意思決定に活用 |
ここで注意していただきたいことは、推奨事項の実施は必須ではなく、柔軟な取り組みが必要だということです。なぜなら、CSデータマネジメントは、様々な要因によって実践方法が大きく異なることが報告されています(Morgan et al., 2005)。例えば、以下のような要因です。
・企業や事業の置かれている市場の変化する速度
・既存市場の変化に適応することが要求されている事業なのか、新しい市場に挑戦することが要求されている事業なのか
・CSデータを含む様々なデータの統合度合い
・CSデータと経営管理との関係性
企業がCSデータを活用できない理由は、上述した要因の違いにより、CSデータマネジメントの方法が企業により大きく異なるからだと考えられます。したがって、企業は、理論的なCSデータマネジメントの各段階におけるや推奨事項を参照しながら、自社の状況に合うCSデータマネジメントの実践方法を模索しなければなりません。自社に合う実践方法を模索する上で、多くの企業は「異業種を含む他社の事例から学びたい」と思うのではないでしょうか?つまり、科学的に推奨されていることの実践や、他社事例からの学びを通じて、自社ならではのCSデータマネジメントを検討していきます。
筆者はCSデータマネジメントの好事例として、スカイマーク株式会社※3(以下、スカイマーク)とトライズ株式会社※4(以下、トライズ)をお勧めします。この2社は、日本生産性本部 サービス産業生産性協議会が主催したセミナーにも登壇されました。スカイマークは、不特定多数の顧客からCSデータを収集し、収集した翌日には社内へフィードバックしています。一方で、トライズは、オーダーメイドで英語学習サービスを提供するために、顧客がサービスに積極的に参加することが求められます。顧客は、コンサルタントに対する満足度をトライズに伝え、トライズはその差を解消しようと努力します。その結果、トライズは顧客の期待と実際のサービスとの差を解消し、顧客の大満足(5段階評価で5点)を獲得します。各社の事例は既に以下のホームページで公開されているため、ぜひご覧ください。

日本生産性本部が実施する国内最大級の顧客満足度調査「JCSI」の紹介です。
サービス産業の約30の業務を対象に毎年調査を行いスコア上記企業を公表し…
- 株式会社 帝国ホテルのホームページより(https://www.imperialhotel.co.jp/special/brand-story) ↩︎
- 積水化学工業株式会社のホームページより(https://www.sekisui.co.jp/company/philosophy/groupvision/) ↩︎
- スカイマーク株式会社の事例:(https://service-safari.jp/case_a/848/) ↩︎
- トライズ株式会社の事例:(https://service-safari.jp/case_a/1872/) ↩︎
【参考文献】
・Hogreve, J., Iseke, A., Derfuss, K., & Eller, T. (2017). The service–profit chain: A meta-analytic test of a comprehensive theoretical framework. Journal of Marketing, 81(3), 41–61.
・Lucia-Palacios, L., Pérez-López, R., & Polo-Redondo, Y. (2020). How situational circumstances modify the effects of frontline employees’ competences on customer satisfaction with the store. Journal of Retailing and Consumer Services, 52, 101905.
・Morgan, N. A., Anderson, E. W., & Mittal, V. (2005). Understanding Firms’ Customer Satisfaction Information Usage. Journal of Marketing, 69(3), 131–151.
・Otto, A. S., Szymanski, D. M., & Varadarajan, R. (2020). Customer satisfaction and firm performance: insights from over a quarter century of empirical research. Journal of the Academy of Marketing Science, 48(3), 543–564.
・重松佳. (2022). 顧客満足度と企業業績の関係性を検証した研究のレビュー. 流通研究, 25(1), 1–26.
・Lovelock, C., & Wirtz, J. (2008). サービス・マーケティング(白井義男[監訳]、武田玲子[訳]).ピアソン・エデュケーション.(原著は2007年刊行)
執筆者:日本生産性本部 顧客価値創造センター 舩先 康平(博士 社会工学)









.png)



