共同輸配送で日本の物流をサステナブルに

日本生産性本部は2025年6月16日、第76期「経済情勢懇話会」の6月例会を都内で開催(オンライン併用)した。当日は、「持続可能なサプライチェーンの実現に向けて」をテーマに、Sustainable Shared Transportの髙野茂幸・代表取締役社長(兼ヤマト運輸グリーンイノベーション開発部部長)が講演した。
同社は、荷主企業や物流事業者が利用・参加する、パレット単位の共同輸配送プラットフォームを、公益性の高い共同事業として提供することを目的に昨年5月に設立され、今年2月から事業を開始している。
ビジョンに「共同輸配送で日本の物流をサステナブルに」、ミッションに「(主にパレタイズ商業貨物において)荷主と物流事業者が行動を変容できる実用性の高い共同輸配送プラットフォームを構築する」を掲げている。国土交通省の物流総合効率化法による出資第一号案件にも採択されている。
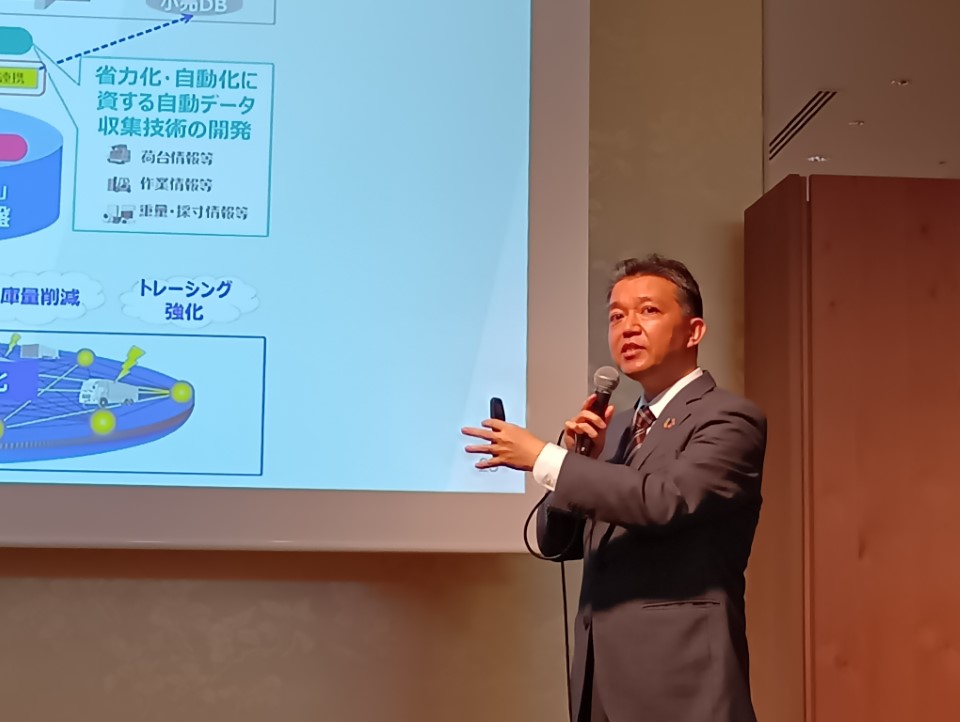
物流業界を取り巻く課題は「改正物資流通効率化法」
髙野氏は、物流業界を取り巻く課題として、改正物資流通効率化法によって、荷主企業には、物流統括責任者の選任や荷待ち時間把握・削減、納品リードタイムの確保、発注の適正化、対応をまとめた中長期計画作成などが求められるようになったことや、働き方改革関連法の労働時間規制によって、長時間労働の抑制(1日あたりの労働時間の上限は11時間38分まで)や日帰り推奨(1日あたりの走行距離の上限は425㌔となり、東京~大阪間を一人で運べなくなった)、日々の労働時間管理、モーダルシフトや中継・共同輸配送の促進、多重下請け構造の是正などが求められるようになったことを指摘した。

日本の物流を持続可能なものにすることを目指す
それらを踏まえ、同社では、「共同輸配送(個社ごとのチャーター便から、複数社のパレット輸送へ)」「中継輸送(個社ごとの長距離輸送から、複数社の短中距離リレー輸送へ)」「定時運行(荷主倉庫の集荷からの対応から、幹線拠点からの定時運行へ)」を実施することで、日本の物流を持続可能なものにすることを目指している。現在、宮城県から福岡県の間で、1日22便を運行しており、今年度には最大80便への拡大を計画している。

同社を活用するメリットとしては、荷主企業にとっては、事業サプライチェーンの持続的向上や温室効果ガス排出量の低減、積載率向上による物流運賃コストの適正化などが図れること、協力事業者にとっては、積載率向上・稼働率向上による収益向上や単位荷物量当たりの温室効果ガス排出量の低減、ドライバーの処遇改善・負担軽減などが図れることが説明された。
髙野氏は、「共同輸配送は皆様のサプライチェーンの持続可能性への契機となる。これまでは物流がビジネスを支えていたが、これからは荷主企業が物流を支える時代になってくる」と述べた。

トップのための昼食会方式の月例セミナー
経済の流れを読み、社会の動きをつかみ、明日の経営に活かす


“一歩先を読む力”を、月に一度東京駅で
生産性新聞2025年7月15日号:「経済情勢懇話会 第3回」掲載分







