第三者の目線で経営診断
中期経営計画づくり
小林電子工業(本社=埼玉県新座市)は、1970年の設立以来、産業用機器向けのプリント配線板製造を主に、基板の設計から部品の実装までを手掛けている。コンサルティングを機に、経営理念や経営ビジョンを定め、中期経営計画の策定を通じて後継者の育成を図っている。今年4月からは完全週休3日制を導入した。

日本生産性本部では、2022年1月から、高村航・主任経営コンサルタントが同社のコンサルティングを行っている。「高村さんは前職で営業担当だったころからよく知っていた。私は2代目で、後継者教育を今から準備しておきたいと思っていたが、高村さんが経営コンサルタントになったこともあり、初めてコンサルティングを受けた」(小林浩・小林電子工業代表取締役)。
「小林社長からは『自社の強みがよくわからない。営業力をもっと強化したい』という話も聞いていた。一度、第三者的な目線で客観的に経営診断から始めませんかと提案した」(高村氏)。
組織分析から改善策~「経営総合診断報告書」を作成
そこで、財務分析、事業分析、従業員満足度調査などの組織分析などを実施し、改善策を立案・検討した「経営総合診断報告書」を22年7月に作成した。
報告書では、①経営理念と具体的なビジョンである「5年後のありたい姿」と事業戦略策定、②明確な経営数値目標の設定と、達成のための事業計画策定、③事業計画達成のための組織・人事戦略の策定の三つが今後の重要経営課題であり、三つの課題を解決すれば、従業員の幸福度が高まって、今後の成長と発展につながると指摘した。
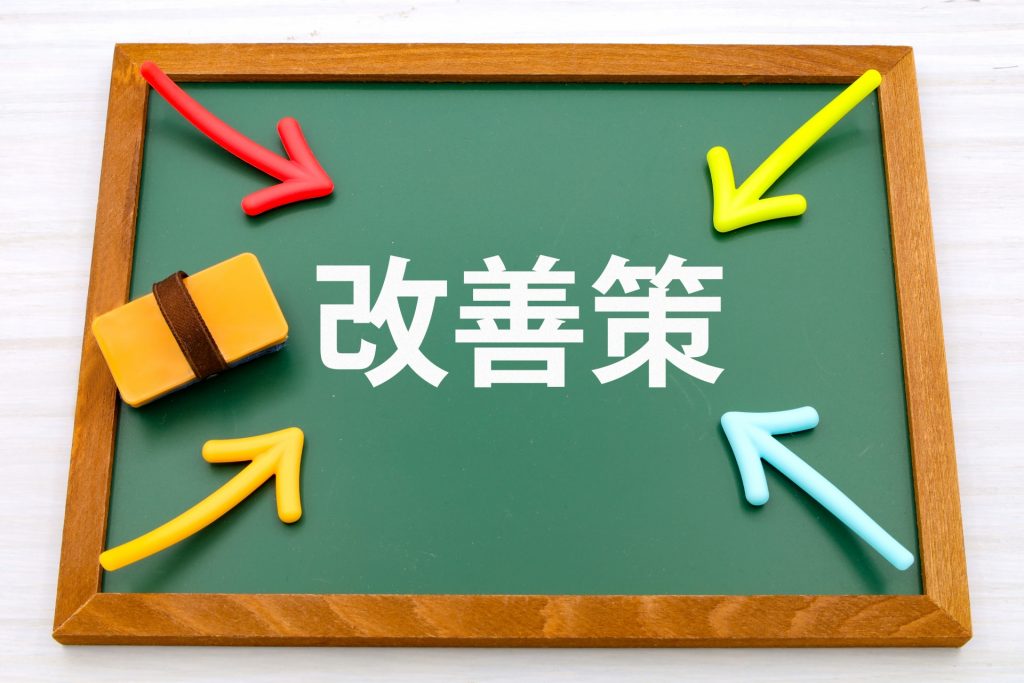
これらの提案を受けて同社では、中期経営計画の策定に入った。小林社長と3人の経営幹部(長男の取締役製造部長、長女の取締役経理担当、娘婿の品質保証課課長)が高村コンサルタントの指導を受け、具体的な内容を検討していった。 できあがった中期経営計画(23年8月~28年7月)では、経営基本方針、事業展開方針、事業戦略と具体策、組織マネジメント、アクションプラン、数値計画などを明示した。
5年度の経営ビジョンと数値目標を明示
経営基本方針では、経営理念、経営ビジョン、行動規範、行動指針を定めた。事業展開方針では、5年後の経営ビジョンを定め、5年目の数値目標を明示した。
事業戦略と具体策では、高利益率を維持したまま販売量を増加させることや、継続的顧客開拓、営業担当者の間接業務削減などに取り組むことを記した。組織マネジメントでは、人材育成や採用の強化、管理会計制度の導入などに触れた。
経営理念(全ての関係者との共存共栄を目指す)と経営ビジョン(安定した収益をあげられる会社にする。仕事にやりがいを感じられ、社員とその家族の幸福度を高める)は、今年3月に開設したホームページに掲載されている。
完全週休3日制を導入
4月17日からは完全週休3日制を導入した。1日8時間勤務の週5日労働だったのを1日10時間勤務の週4日労働(平日に祝日のない週は金曜日が休日)に変えたので、週の労働時間は変わらず、給料も変わらない。
「一番のねらいは採用活動における差別化だ。週休3日制は電子業界のプリント配線板製造企業では業界初だと思う。現状では人手不足ではないが、今後の採用活動ではかなり有利に働くのではないかと期待している。主要顧客には、週の労働時間は変わらないから納期の遅延はないと説明し、理解を得た。
導入してまだ間もないが、生産性が高まり、効率よくモノが回るようになった。稼働日数が減り、電気代が軽減できたのも大きい。何よりも社員のモチベーションが上がり、いいこと尽くめだ」(小林社長)。「スキルマップの作成、多能工化の推進、作業の手順の入れ替えなどによって、現場の作業改善が進み、それが週休3日制導入のとっかかりになった」(高村氏)。
IT化施策

遅れていたIT化にも手を付けた。クラウドサービスの「キントーン」を導入し、業務や作業の見える化を行い、効率化や共有化を促進させた。それらの取り組みの結果、53期(昨年8月~今年7月)の決算は、3期連続の黒字で、損益分岐点は9ポイント下がり、一人当たりの労働生産性も上昇した。
「様々な調査や分析を実施して、経営幹部で議論しながら、ようやくこれが自社の強みではないかというものを認識できるようになった。今後はそれを武器にして、自信を持って営業活動を進めていきたい」(小林社長)

小林浩・小林電子工業代表取締役の話
社員のベクトルを同じ方向に
高村コンサルタントは私よりも若いが熱心で非常に頼りになる。相当、努力を重ねてもらって、弊社に寄り添ってもらっている。 長男は製造の指揮官として采配を振るっていたが、経営、財務、営業には関わっていなかった。中期経営計画策定の過程で、経営幹部の3人は、高村コンサルタントから、戦略や財務、マネジメントを教えてもらった。長男と娘婿の2人には今後、営業を経験させていく予定で、営業力を強化していきたい。
中期経営計画で作り上げた理念やビジョンを従業員に周知徹底し、みんなのベクトルを合わせていきたい。8月1日には全従業員を集めて、中期経営計画の説明会を実施した。理念やビジョン、行動指針を発表して、従業員が携行できる名刺サイズのカードもつくった。これからは朝礼などを活用して理念の浸透を図っていく。
今回のコンサルティングの一番の成果は、経営幹部全体で数字に向き合い、経営を真剣に考えるきっかけになったことだ。中期経営計画をつくって終わりではなく、PDCAを回して進捗を管理しながら次の打ち手を考え、会社の力を蓄えていきたい。予想できないリスクがいつ訪れるかわからない。危機に直面したときでも乗り越えられるような経営者づくりが今後の課題だと思っている。
高村航・日本生産性本部主任経営コンサルタントの話
自社の当たり前に向き合う
コンサルティングの成果が出た背景には、小林社長の長期的な視点と謙虚な姿勢、値上げの断行があると思っている。
将来の事業承継を見据え、先送りせずに今から手を打ち、経営改革を行った。「困らない経営」「持続可能な経営」を掲げ、従業員の生活を守ろうという意識が非常に強い社長が、提言をしっかり受け止め、謙虚に着実に施策を実行されていることに敬意を表したい。
小林電子工業は売上高約3億円、従業員は22人(パート含む)の中小企業だが、日々自分たちの行っている仕事の成果を信じ、取引先にしっかり説明をして値上げを了承してもらったことで、同社の損益分岐点は大きく改善され、付加価値率も高まった。
私は、社歴の長い中小企業で強みのない企業はないと思っている。数十年以上続いている企業には何か強みがあるはずだ。当たり前だと思っていることが強みであることに気づいていない企業や、自社の強みを明確に言語化できていない企業が多い。それを洗い出して明確に言語化し、再定義することはとても大事なことだ。
「VRIO分析」(経済的な価値、希少性、模倣困難性、組織の四つにおいて、自社の経営資源が他社に比べてどのくらい競争優位があるかを分析するフレームワーク)に「独自の歴史的条件」(組織の歴史が競争優位性の形成に影響を与える)という概念があるが、長い時間をかけてその企業が獲得したものは他社がまねできず模倣困難性が高い。自社の当たり前だと思っているものをもう一度見直してほしい。

日本生産性本部 主任経営コンサルタント
資格:
中小企業診断士、国家資格キャリアコンサルタント
経歴:
慶應義塾大学商学部卒業後、株式会社キーエンスにて17年間勤務し、コンサルティングセールスおよび営業戦略・販売戦術立案、チームマネジメントに携わる。
生産性新聞 2023年11月15日号:「変革の現場」2023年度第4回 掲載分
 生産性新聞 | 生産性運動について | 公益財団法人日本生産性本部生産性新聞のページ。生産性新聞は 生産性運動の広報紙として、「生産性」・「経営」・「労働」を3本柱に、質の高い情報をタイムリーに紹介します。公益財団法人日本生産性本部
生産性新聞 | 生産性運動について | 公益財団法人日本生産性本部生産性新聞のページ。生産性新聞は 生産性運動の広報紙として、「生産性」・「経営」・「労働」を3本柱に、質の高い情報をタイムリーに紹介します。公益財団法人日本生産性本部








.png)



